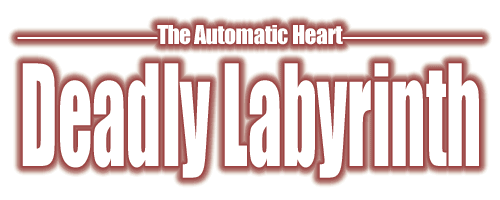
[11]
“謎の声”によるゲームスタート宣言後――第一階層中央部北側の部屋に逃れていたレイスたち一行は二時間におよぶ話し合いの末、一瞬にして七日もの時間が過ぎ去った原因を“現実の体が病院に運ばれた”と推測することにした。
VRN社は利用者の個人情報を把握している。そもそもアンデルフィア=ローカル場には声紋と同じ特性があり、これを個人認証手段として利用している。ゆえに利用者を特定することは簡単だ。また、VRN社は積極的にPVの医療利用も進めているため、病院の確保もそれほど難しくないはず。無論、だからといって“謎の声”の言葉が真実とは限らない。愉快犯的なハッカーが時刻表示を早めただけかもしれないし、そうでなくてもいずれVRN社の社員がなんとかしてくれる可能性がある。
だが――
「最悪の事態を想定して動いたほうが懸命だ。異論は?」
と告げるレイスに反論できる者はいなかった。
TVなどでPV反対派が主張していた“デスゲーム”と、状況があまりにも符合している。また、仮に犯人がハッカーだとすると、下手に外部から助け出そうとすると何をやりだすかわかったものではない。最悪、ここぞとばかりに全プレイヤーを殺害する可能性すらある。心停止程度ならまだ回復の余地もあるが、神経系にダメージを与えられたら、死ぬよりも辛い日々が待ち受けているかもしれない……
そこまでのリスクを外の人間が行うだろうか?
他にも様々な意見が出たが、いずれも“現実の体が病院に運ばれた”という推測を前提にした上で語られ続けた。
こうして二時間後、一同は手始めにコロシアムへと戻り、他のプレイヤーとも協議することにする。
しかし――
「知るかよ」
「ほっといてよ」
「くるな! くるんじゃねぇ!」
“謎の声”の衝撃から冷め切っていないのか、それとも絶望と諦めが空気感染してしまったのか。コロシアムに残っていた三千名近いプレイヤーは、軒並み、急に現れた――かのように見える――レイスたち一行を胡散臭(うさんくさ)げに見るだけだった。
「……やはり私は最悪の事態を考え、攻略に専念したい。賛同する者は?」
三十名近いプレイヤーが賛同した。
そこから一週間――二十八名からなる集団は一日六時間の冒険を続け、昨日早朝、最精鋭十二名からなる二パーティを第二階層に派遣。そして今日十八時、迷宮内で一泊した二パーティは第三階層に降りるストーンサークル発見の知らせと共に、一人も欠けることなく、無事、生還した。
ようやくゲームが動き出したのである。
◆
あの悪夢の初日の時に逃げ込んだ部屋を、レイスたちは“会議室”と呼んでいた。
「待たせた」
部屋に入ったレイスは軽く上げた手を振り下ろした。次いで、遅れてやってきた面々がドヤドヤと二×三ブロックの部屋に入ってくる――かと思うと、次々とアイテムウィンドウを展開させ、収納していたテーブルや椅子、無数のランタンをテキパキと配置していった。
会議室にはレイスに賛同した二十八名全員が集まっている。家具類の見張りを手近なプレイヤーに、前金を渡して警護するよう頼んでいたため居残り組が遅れてやってきたのだ。無論、貴重品はすべて収納済みだ。家具類も理屈的には盗みづらいと考えられるため、数時間の留守であれば大丈夫だろうと一同は考えている。
「うほっ、いい料理!」
先に待っていた探索組の一人――ランスロットが具現化されたばかりのフライドチキンを食べようとした。
会議室に入った居残り組の面々が、先ほどから次から次と、料理の載った小皿や飲み物を並べていたのだ。これだけのフード系アイテムが一挙に並ぶのは壮観である。ランスロットでなくとも飛びつきたくなるのが普通だろう。
だが、即座にレイスの鋭い声が響いた。
「そこっ! 食べるな!」
「ヒャッ!」
驚いたランスロットはフライドチキンを放り投げてしまい、お手玉をしながらどうにかキャッチ、ホッと胸をなで下ろした。
笑いが起きた。
「……あほ」
その隣をクロウが呆れながら通り過ぎる。その際、彼は小皿をひとつ掴んでドアに向かおうとした。
「そこっ!」
「見張り」
クロウは隔壁のようなドアの境目に腰を下ろした。
こうしていれば、ドアは閉じない。しかも、部屋のドアが突き当たりの右壁にあるため、背中側から強襲される心配も無い。
「ったく……」
レイスはため息をつくと、視線のあったリーナに顎でクロウの相手をするよう促した。彼女はうなずき、グラス二つとジュース瓶、椅子用の座布団二つを持って彼のもとへと向かった。それを確かめてからレイスは装備を外すよう、皆に告げることにする。
軽装な魔術師のプレイヤーはそのままの格好で、フルプレートメイルを身につけた重戦士と聖職者のプレイヤーは、初期装備であるTシャツにバミューダパンツという格好に変更してから、それぞれ椅子に腰掛けていった。なお、軽戦士はクロウとリーナしかおらず、二人ともブーツ、パンツ、ベルト、袖をまくったロングTシャツという格好のため着替える必要は無い。
「では、乾杯だ」
レイスは六人掛けのテーブル五つに分かれた皆を一瞥すると、最奥のテーブルに腰掛ける赤毛の青年に向かって意味ありげな笑みを投げかけた。
「リーダー、音頭を頼む」
「リーダーはそっち」
赤毛の青年――バッシュは笑いながら立ち上がった。
「えーっ、とりあえず探索組、お疲れ様でした。居残り組には、心配かけさせて申し訳ない。帰りが遅れた理由はあとで詳しく説明しますが、まぁ、適当に探索組から聞きだしてもOKってことで。OK?」
レイスに尋ねると、彼(彼女)は苦笑まじりにうなずき返した。
「じゃあ、そういうことで……」
バッシュは咳払いをすると一歩下がり、椅子を横向きにした。
そして。
「――おい野郎ども!」
ダンッ!――と椅子に足を乗せる。
「今夜は無礼講だ! 好きなだけ飲め! 食え! 騒げ! 一、二、三――乾杯!」
「「「「乾杯!」」」」
賑やかな宴が始まった。
◆
「乾杯ッ」
「……」
ドア付近でも、リーナが強引にクロウのグラスに自らのグラスをぶつけていた。もっともクロウの頬は少しばかり緩んでいる。不機嫌というわけではないのだ。それどころか、彼の中にあるのは生還したことへの安堵の思いだった。
(どうにか生きて帰れたな……)
グラスのコーラを飲みつつ、ようやくクロウは一息ついていた。
第二階層の大半は、第一階層北西部にあるドア地獄と同じものだった。不幸中の幸いは出てくる敵が第一階層のコボルト、ゴブリン、グレイウルフ、ミノタウロスの、武装や色が微妙に違うバージョンばかりだったという点だろう。データ的には第一階層より強いらしいが、基本的な攻撃パターンは何も変わっていないため、大きな被害を出さずにすんでいる。もっとも、ドア地獄のせいで移動に時間が掛かりすぎたのだが。
――このまま帰れなくなったら
――永遠に同じ部屋が続いたら
最初は楽勝ムードで進んでいたが、次第にクロウを含む十二名全員が不安を抱き始めた。
そんな中で、ひとり陽気に笑っていたのが、リーダーのバッシュである。
――なに、この程度、アフリカを縦断した時に比べれば大したことないって。
リアルの彼は、学生時代、大学を休学してまで世界各地を歩き回ったバックパッカーだったらしい。そんな彼が語る旅行話は、探索組の緊張を和らげる良い薬になった。
――インダス河に付いたら、もう感動しまくったわけよ、これが四大文明を生んだ河のひとつなのかって。それで思わず足だけ入れていこうって思ったんだけど、ふと川上みたら、こーんなちっちゃい男の子が小便してんの。ズボン全部下げて。
――そのおっさん、何度も“おまえは中国人か?”って尋ねてくるわけ。“違う、ジャパニーズだ”って答えたら、急に笑い出して、“日本は素晴らしい。アメリカと戦った”とか言い出すわけ。おい、そりゃ、何十年前の話だよって――おおっと、来た来た。さーて野郎ども! It's show time !
「……どうかした?」
隣に内股になって座っているリーナが不思議そうに尋ねてきた。
頬を撫でてみる。思い出し笑いをしていたらしい。
クロウはコーラを飲みつつ、バッシュの姿を探してみた。
すでに席を立ったバッシュは、別のテーブルの面々に絡んでいるようだ。そこで笑いを起こし、また別のテーブルに移動している。冒険から帰ってきたばかりだというのに、疲れなど微塵(みじん)も感じられない。
「タフだな……ってな」
「……だね」
クロウの視線をたどったリーナも、笑いを起こしているバッシュの姿を捕らえていた。
だが、それも一瞬のこと。
「リーナちゃぁああああん!」
両手に皿を持ったランスロットが駆け寄ってくる。
「はい、リーナちゃんのケーキ。どれがいい? 全部でもいいよ?」
「えっ――――――」
「こらーっ!」
ドカドカと駆け寄ってきたマコが、しゃがみこんだランスロットの後ろ首を鷲づかみにした。
「あんだけクロウに助けて貰って邪魔をするってのはどういう神経してんの!」
「そ、それとこれとは関係ないだろ!」
「うっさい! 問答無用! あっ、ボイル! ちょっと手伝って!」
後ろに並べたジュースを取りに行く途中だった巨漢のボイルがコクリとうなずき返した。
「こ、こらぁ! やめろー! 人権侵害だ! はなせー! こらぁ!」
もがくランスロット。
無視して引きずるマコとボイル。
皆がドッと笑う。
「はいはい、お姉さんの晩酌に付き合ってね」
椅子に座らされたランスロットの首筋に、背後からキリーが胸を押し当てつつささやきかけた。途端、ランスロットは顔を真っ赤にして全身を緊張させる。そこで再び、ドッと笑いが起きた。
(これで根に持つようなことも無いんだからな……)
これもある種の才能なのだろうと思わずにいられないクロウだった。
◆
「迷宮が広がってる?」
「見るか?」
馬鹿騒ぎが続く中、クロウはリーナとマップ情報を共有した。
当初の仕様では全階層が百×百ブロックということになっている。だが第二階層を細かく調べた結果、全体が百二十×百二十ブロックであることが判明していた。
「そっか……それで時間が……」
納得とばかりにリーナがうなずく。
「詳しいことは他の連中に聞けよ」
と言いたかったが、クロウはその言葉を飲み込むことにした。
なにしろ黙っていると、どうにも居心地が悪い。だが何か話そうにも話題がない。結局、クロウが話し始めたのは探索組の帰還が遅れた理由という、実に味気ない場つなぎの話題だった。
しかも、その理由は“広さが増した”という至極単純なものだったりするから苦笑するしかない。だが、縦横が二〇ブロック分増えたことで、面積は第一階層の一.四四倍に広がっている。それと気づかず、クリーチャーと戦いながら歩き回って結果、睡魔とも戦わなければならなくなったのだから“たかが広さ”と侮るわけにもいかない。
なお――迷宮内では様々な生理欲求が省略されている。食事・料理はアイテムとして存在するが、本来はマイルームで楽しむための軽食にすぎず、味覚・触感を刺激する以上の役割を持っていない。そもそも空腹を感じることも、飢えで死ぬことも無い。当然、排泄もない。新陳代謝により垢が溜まることもないし、疲労こそするが、少し休めば回復する。その際、汗をかくようになったが、乾くと完全に消え、ベトつくようなこともない。
例外は睡眠だけ。
生身の脳が疲れるからだろう、睡眠欲求だけはプログラムとして設定せずとも、最初から存在しているようだ。しかも、我慢しようとして我慢できる仕様ではないらしい。限界まで脳が疲労すると、まるで電源が突然切れたかのように眠ってしまうのが通例なのだ。そのため早朝九時頃に出発した探索組は、二十時頃、第三階層に降りるストーンサークルを見つけ出したはいいが、帰り道で睡魔に破れる者が現れては大変だと判断。交互に見張りを立てつつ、一眠りしてから戻ることにしたのだ。
ちなみに居残り組だったリーナも、午後になり、寝床の見張りから解放されたため、自分の寝床でクロウのことを心配しつつ、いつしか眠ってしまった――というのは秘密である。
「おそらくココから先、もっと戻っていられなくなるなるだろうな」
クロウはサンドイッチに手を伸ばしながらも、試しとばかりに降りてみた第三階層のことを思い出した。
第二階層は第一階層北西部と同じドア地獄だった。
そして、第三階層は北部と同じ迷路地帯だった。
出てくる敵はウッドゴーレムばかり。丸太に関節付きの両腕と両足がついているだけというオモチャのようなクリーチャーだが、珍妙な動きに加え、それまでのクリーチャーに付き物だった攻撃命中時の“痛がる”という隙を作らないなど、厄介な特徴を幾つか持ち合わせた難敵である。
しかし炎の魔術に弱い。
おそらく第三階層は魔術師のMPが勝負の分かれ目になるだろう――クロウはそんな自説をリーナに語って聞かせた。
「う〜ん……そうかなぁ」
「んっ?」
「だってさ、落としてる武器とか、中華系なわけでしょ? だとしたら木人拳なんじゃない、三階って」
「木人拳?」
「知らない? 映画の『少林寺木人拳』。まだ深夜のTVとかで流してるじゃない。若い頃のジャッキー・チェンが主演してるやつ」
「……監督だろ?」
「昔は俳優だったの。それも超有名なアクション俳優。ちなみにあたしの憧れの人」
「あのジジィが?」
「だーかーらぁ! 昔は違ったの! あんた、DVDとか見ないわけ? ブルース・リーとかジャッキー・チェンとかサモハン・キンポーとかフランキー・チェンとか」
「渋いな」
と横から言葉を挟んできたのはレイスだった。
「邪魔するぞ。どうも色っぽい話しは無さそうだしな」
「はぁ?」
クロウが嫌そうな顔でリーナの前にあぐらをかくレイスを睨みつつけた。
「話は戻るが――木人拳というのは、案外、正しい見方かもしれん。ウッドゴーレムの動きはどうだった? 素早かったか?」
「……まぁ、そこそこ」
「だとしたら魔術師には辛いぞ。照準は空間に固定されるからな」
「……空間?」
「だから避けることもできる。おまえのように」
レイスはニヤリと笑った。馬鹿にされたように思えたクロウはムッとしつつ、コーラを一気に飲み干した。
「……魔術師には辛いって?」
「その通り――飲むか?」
レイスはビール瓶を持ち上げた。
クロウは無言で、リーナが持ち上げようとしていたコーラ瓶を奪い、手酌した。
「だったらどうなる」
「どうもならん。戦士系が足止め、魔術師が攻撃、聖職者が補佐――これまで通りだ。まぁ、相手が素早いとなれば、先読みとロックオンのいい練習ができそうだな」
「だから大した速さじゃないって」
「そうでも無かったじゃないですか」
新たに割り込んできたのは肩ほどまで伸びる茶髪を揺らした聖職者マサミだった。名前、顔立ち、体つきのいずれをとっても中性的だが、Tシャツに包まれた胸元はわずかに盛り上がっている。外装も中身も正真正銘の女性なのだ。
「メンバーの中でまともに攻撃を当てられたの、最初のうちはクロウさんだけでしたし――あっ、これ、ポテトチップとポップコーンです。食べますか?」
「感謝。で、どんな感じだった?」
レイスは受け取りながら尋ね返した。
「えっと……どう言えばいいか…………」
「座りますか?」
リーナが立ち上がり、座布団を差し出した。
「あっ、でもリーナさんも――」
「まだありますから」
リーナはさらに二枚の座布団を取り出し、ひとつをレイスに渡した。
「動きが面倒なだけだって……」
ひとり、今になっても座布団に座らず、ドアの境に背を預けて座るクロウがボソボソッとぼやいた。
「どういう動きだ?」
レイスは座布団の上にあぐらをかき、マサミにも座るよう促しつつクロウに尋ねた。
「上下の区別が無い」
クロウは皿を一瞥し、フライドポテトの横に空き地を作ってから一本ずつ並べていった。
「胴体は丸太。X面に回る腰部と、横に突き出た棒が四本あって、先端にXZの平面ジョイントがひとつずつ付いてる。これとつながった棒は、さらに先端でYZの平面ジョイントがひとつずつ。先端は板の中央にXZに回る棒と、その棒の中央でYZに動くジョイントがある」
クロウが並べたフライドポテトは、両手両足の長さが同じという、棒で作られた不格好な人形にしか見えないものだった。
「これが四肢全部に共通しているせいで、逆立ちしても普通と変わらないことになる。顔は胴体の両端、前後についてるから、余計、混乱する。ただ、可動部が限定されている分、下になってるほうの動きを見れば、次の動きは一目瞭然。大した敵じゃない」
クロウは「以上終わり」という眼差しを一同に向けた。
レイスはいつも通りの嘲笑に見える笑みを浮かべていたが、リーナとマサミは目を輝かせながらクロウを見返していた。おもわず「なんだ、その目は」と言いそうになったが、それよりも早く――
「すごいですよ、クロウさん! そこまで観察していたなんて!」
「ホント、ホント! もしかしてクゥって、いつも観察しながら戦ってるわけ!?」
二人は興奮気味に語りかけてきた。
「……誰でも気づくだろ」
クロウは憮然とした表情で顔を背けた。
「またまたぁ、照れちゃってぇ」
リーナはクロウの肩を何度も叩いた。不快そうコーラを飲むクロウだが、微妙に頬が緩んでいる。
「ひとつ聞くが」とレイスが尋ねた。「おまえから見て、ここのクリーチャーの動きは構造の制約を受けているか?」
「多分」
クロウは短く答えた。だが、続きを話せとばかりにレイスが黙り込んだため、空いている左手でガリガリと頭をかきながら言葉を続けた。
「パラメータがあるから無茶はできん。そういうことだろ」
「パラメータ?」
リーナが尋ね返した。
「数値だ、数値。耐久力とか何だとかの――でも、あくまで『GUN ARM FRONTIER』ってゲームではそうだったってだけの話だぞ」
「なるほど、そういうことか」とレイス。
「どういうことですか?」
マサミがビールをお酌をしながらレイスに尋ねた。
「なに、クリーチャーも無茶な動きはできない――そういうことだな?」
「今のところ、だ」
クロウはグラスを置き、背伸びをした。
「ん〜〜〜っ……細かいことは開発者に聞け、開発者に。そもそもリアルすぎるんだ、このゲーム。考えれば考えるほど頭の中がこんがらがってパンクしそうだ、マジで」
「あっ、寝るなら毛布とかあるけど――」
「いい。会議始めたら起こせ」
クロウは膝を抱えたまま顔をうつむかせ、目を閉ざした。
「見張るんじゃなかったのか?」
そんなレイスのツッコミも無視して、クロウはあっという間に寝息をたてはじめた。
実はこれでもかなり疲れていたらしい……
To Be Contined
Copyright © 2003-2004 Bookshelf All Right Reserved.