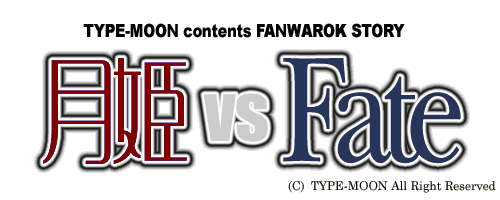
※本作は『 TYPE-MOON 』の作品をベースにした二次創作物です※
[06]
-
1
音がした。
古い、たてつけが悪くて蝶番も錆びて無闇に重い、廃墟の扉が開く音が――
(廃墟?)
士郎の意識が一気に覚醒していく。
瓦礫を踏む足音は、士郎が横たわるベッドから離れたところで止まった。
足音のヌシは何も語らない。
「くっ……」
体を起こす。頭が痛い。二年前に感じた“あの頭痛”とどこか似ている。
「………………シロウ……」
柔らかい声が聞こえた。とてつもなく懐かしい響きだ。
瞬間、士郎の意識は完全に目覚めた。
目を向ける。
そこには、グッと唇をかみしめ、わずかに顔を背けている青い騎士の姿があった。
「……セイバー」
その名を告げるだけで二年前のわずか数日間が昨日のことのように思い出される。
セイバー。
聖杯戦争で共に戦った高潔なる騎士の王。
その正体は伝説に名高いアーサー・ペンドラゴン――そう呼ばれる存在になることを自らの意志で選んだ少女。歴史に真の名を残すことなく、伝説に少女であったという影も残さず、ただひたすら“アーサー・ペンドラゴン”として生き抜いた鋭利なる一本の剣。
「……おかえり」
告げたい言葉は他にもたくさんあった。だが、彼の口から紡ぎ出されたのは、万感の思いを込めた他愛も無い言葉だった。
理性の一部が謝るべきだと告げている。
桜を助けるため、“
それは、決してぬぐうことのできない衛宮士郎の罪。
たとえ錯乱した桜に操られていようとも、彼女に手にかけた衛宮士郎の罪は、未来永劫、重くのしかかり続ける。
だからだろう――
「……」
セイバーは無言のまま、顔をそむけていた。
その頬が少し赤らんでいる。まるで、恥じらいを見せる乙女のように――
(――えっ!?)
瞬間、彼は“ありえざる過去”の記憶を意識した。
「あっ! い、いや! アレは! えっ、でも――ちょ、ちょっと待った!」
士郎はあわてた。
ここは冬木市郊外、樹海と呼ばれる場所――アインツベルンの森――の一角にある廃墟の中だ。
一度として近づいたことのない場所だ。
だが、彼はこの場所を知っていた。体験していないはずの別の過去を、士郎はしっかりと思い出せたのである。
それは士郎がセイバーと共に戦い抜いた記憶だ。英雄王と黒い聖職者を二人でうち破り、全てが黄金に染まる世界で永遠の別離を迎えたという、“ありざる記憶”だ。問題なのは、その記憶にある“廃墟で起きた出来事”が――
「世界線が交わっています」
セイバーは頬を赤らめたまま、真剣な表情で慌てる士郎に語りかけた。
「一度だけ、異なる選択が為された世界を知り合いに見せてもらったことがあります。徴税を緩めた結果、軍の物資が不足し、我々が大敗してしまう光景でした。そのような異なる選択が為された世界が、この世には無数に存在するそうです。しかし、“魔法”の中には、そうした異なる世界の流れを交えるものがあるとか――」
「――そうか、遠坂の!」
「リンの?」
わずかにセイバーの表情が曇る。だが士郎はベッドにあぐらをかきながら体を彼女に向け、勢い込んで話し続けた。
「そう、遠坂の魔法……じゃなくて、えっと……遠坂の五代か六代か前の人が師事した人が“魔法使い”なんだ。その“魔法使い”の“魔法”が並行世界に――世界線だっけ? それに関係するもので――いや、でも、遠坂はまだ使えないって言ってたし、真似事みたいなことをやったのも、二年前の《大聖杯》での戦いの時だけだって……」
「それかもしれません」
「それ?」
「二年……でよろしいのですか、前の聖杯戦争から経過した時間は」
「あっ、うん――いや、聖杯戦争は終わった。間違いない。そもそも《大聖杯》はイリヤが閉ざしてくれたんだ」
「えっ――?」
「最後に俺を助けてくれたんだ。だからもう《大聖杯》は……えっ? あれ?」
だとすれば、セイバーが召喚されるはずなどありえない。
しかしセイバーはここにいる。
士郎は自らの左手の甲を見た。そこには赤い刻印が浮かび上がっている。令呪だ。
聖杯戦争におけるマスターの証。サーヴァントに対する三つの絶対命令権。発動時には魔法に匹敵する神秘を実現できるという特殊な魔術刻印。その力は空間を歪め、別の場所に瞬間転移させるぐらい軽々とこなしてしまう。そんな聖杯戦争の象徴とも言うべき令呪が再び士郎の左手の甲に浮かび上がっていた。
「……シロウ」
顔をあげると、セイバーは真剣な表情で彼を見据えていた。
彼女が告げた。
「私は――死にました」
「――えっ?」
セイバーは半歩下がり、不可視の剣を具現化させた。
と、ふわりと柔らかな風が廃墟の中を吹き抜ける。
見えざる剣が、その姿をあらわにした。
士郎はギョッとした。
「まさか……」
「はい。湖の妖精に返しました。ですから私は、なぜここにいるのか、わかりません」
彼女が手にする剣は、ただの剣だった。
いや、ただの剣というのは失礼だろう。“剣”の極みである士郎には、刀剣に限定された根源認識力がある。ゆえに、彼女が手にする剣が霊性を帯びた名剣であることぐらい、一瞥するだけで理解できた。それこそ下手な概念武装など足下にもおよばない。だが、名剣は名剣。そして彼女はアーサー王だ。
アーサー王が手にするべき剣は、ただの名剣であってはいけない。
「《
士郎は混乱した。
令呪がある以上、セイバーはサーヴァントとして召喚されている。そうである以上、彼女はアーサー王の英霊として召喚されたはずだ。しかし、アーサー王の象徴であるエクスカリバーを所持していない。いや、確かに伝説では死去する際、アーサー王はエクスカリバーを湖の妖精に返している。だが、それだとますます話がおかしい。
セイバーは死去する直前、存命中に聖杯を獲得することを条件に《世界》と取り引きをした特殊な英霊だ。そのため、彼女の魂――アーサー王という概念――は、時代を超え、聖杯探索に関わる様々な英霊召喚に応える形で顕現するが、失敗すると、再び死する直前の体に戻り、また別の聖杯探索の召喚に応じる――ということを繰り返している。
よって、この状態のアーサー王は必ずエクスカリバーを手にした状態で召喚される。
無論、聖杯探索が成し遂げられた場合、死する体に戻った彼女はエクスカリバーを返却した状態で命を終え、正式な英霊に昇格する。この時の彼女はエクスカリバーを所持していない。なぜならそれは湖の妖精の手に返されているからだ。
しかし、それはあり得ない。
「聖杯は……手にいれていないんだよな?」
念のため士郎は尋ねた。
セイバーはこくりとうなずき返す。
おかしい。【矛盾】している。なぜそんなことが起こりえるのか。
(いや、そもそも……)
聖杯戦争のあと、士郎は彼なりにアーサー王の伝説について調べてみた。その結果、本質的な【矛盾】を彼は見つけ出していた。
伝説によれば、アーサー王は決して聖杯を手にしない。聖杯探索そのものに成功した騎士はいたが、聖杯をアーサー王のもとに届けたという伝説はひとつとして残されていないのだ。だからこそ
それは大いなる【矛盾】だ。
伝説の具現体であるアーサー王は聖杯獲得を条件に《世界》と取り引きした。
しかし、アーサー王の伝説では、聖杯は決して手に入らないとされている。
聖杯を手にした瞬間、アーサー王は伝説と【矛盾】した存在になる。
アーサー王であって、アーサー王では無い存在に……
「……シロウ」
か細いセイバーの声。考え込んでいた士郎が顔をあげると、セイバーは顔をうつむかせ、自らの体をギュッと抱きしめていた。
「私は……私なのですか……?」
答えるべき言葉を、士郎は見つけられなかった。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「どうしてあなたが」とシエルはアルクェイドを睨んだ。
「それはこっちの台詞よ」
アルクェイドは溜息をつきつつ、髪をかきあげた。
もっとも、二人ともなぜこの二人が一緒にいるのか、だいたいの察しはついている。
かつてシエルは“アカシャの蛇”と呼ばれる特殊な死徒――下級の吸血種――に躰を奪われていたことがある。その頃の彼女を殺したのは他でもない、“蛇”の生みの親である真祖の姫、アルクェイド本人だ。
その後、シエルは死ねない躰になった。その身に残る“蛇”の残滓が肉体という世界の崩壊を許さなかったからだ。ゆえに彼女は転生を繰り返す“蛇”を追いかけ、二年前、ある町でついに“蛇”を追いつめた。
一方、アルクェイドも“蛇”を追いかけ続けた。彼女は“蛇”を死徒にしたことで、自らの力の一端を“蛇”に奪われていたのだ。追いかけていた理由はそれだけではないにしろ、彼女は“蛇”の転生体が現れてはこれを殺し、再び転生体が目覚めるまで長い眠りに付く――ということを続けながら、二年前、ある町でついに“蛇”を追いつめた。
そこで二人は“蛇”の“死”に巡り会った。
成し遂げたとは言えない。“蛇”を殺したのは、特殊な魔眼を持った一人の少年だ。彼がいなければ“蛇”は再び新たな肉体を得て転生していただろう。それを考えれば、二人がしたことは、彼の背中を押したぐらいでしかない……
「因果なものよね」
アルクェイドはもう一度溜息をついた。シエルは沈黙をもって、それを肯定した。
ここは濃霧に包まれた樹海の中。明るいところを見ると、一応、時刻は昼らしい。
「何が起きたかわかりますか?」
シエルは周囲を警戒しながら尋ねてみた。
「推測だけど」
と、アルクェイドも周囲を眺める。
「因果律が崩れたのよ。並行世界全てを見渡しても、存在してはいけない出来事が起きてしまった……だから《世界》が、それを修復しようとした。それに巻き込まれたってこと」
「どうして私とあなたがここに?」
「【矛盾】の本質にわたしたちが関係しているってことなんじゃない? あと、この場所もね。ただ、“意味の距離”の近い、遠いって問題が残るわ。仮に【矛盾】の本質に“あいつ”が関係しているなら、志貴だって無関係じゃないでしょ。でも、ここに志貴はいない。同じ意味で、この場所が【矛盾】の本質から“遠い”かもしれないし、“近い”かもしれない」
「……“蛇”が生きていると言うのですか?」
「死んでるわよ。それは確実。だって、志貴が“殺した”んだもん」
「じゃあ……」
シエルは自らの右拳を見下ろした。
「これはどう説明しますか」
彼女はアルクェイドに見えるように掌を指しだした。
強く拳を握り、爪を食い込ませたのだろう。シエルの掌には血がにじみ出ていた――が、それも一瞬のことだ。次の瞬間には、傷が完全に消え去っていた。漏れだした血も、ウソであったかのように消えている。
「……そこが不思議なのよ」
アルクェイドは驚きもせず、目を閉ざしながら右手を自らの胸に押し当てた。
「“あいつ”は死んでる。それは間違いない。“あいつ”に奪われた力も、今、ここにある。それも間違いない。でもね――」
彼女は目を開けた。
「感じるのよ。“あいつ”の気配」
無限転生者――ミハイル・ロア・バルダムヨォン。真祖の姫に血を吸わせ、それによる猛りで真祖の姫自身に他の真祖を滅ぼさせた誘惑の死徒。“アカシャの蛇”と呼ばれるアルクェイドとシエルの仇敵。二年前の事件で遠野志貴により“死”を与えられたはずの存在……
「どういうことですか?」
シエルが尋ねた。
「だから、【矛盾】が起きたんだってば」
アルクェイドは濃霧を見上げた。
「死んだはずの“あいつ”が生きている。だからシエルの復元能力も戻っている。でも、わたしには“あいつ”に奪われたはずの力が残っている。【矛盾】してるでしょ? でもね、その【矛盾】を《世界》が修正していない。もっと大きな【矛盾】、《世界》そのものを壊しかねない【矛盾】が起きたからよ。多分だけど……」
アルクェイドは濃霧を睨んだ。
「その【矛盾】も治りきらなかったから、妙なことになってるのよ」
彼女の視線の先にはボンヤリと浮かぶ月のような太陽が輝いていた。
To Be Continued
Copyright © TYPE-MOON / Bookshelf All Right Reserved.