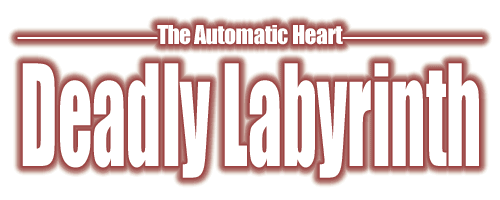
[41]
三十九日目午後八時頃――三百四十名に膨れあがった独立派は、攻略隊の協力により、第三階層への完全避難を成し遂げていた。落ち着いた先は、リカバリィポイント前の蛇行した通路だ。北側と西側の分岐路に歩哨さえ立てておけば、クリーチャーに怯える心配の無い、安全地帯になりえる場所でもあったからだ。
ちなみにエレベータールームに近い分岐路は、北側にあるT字路のほうだ。だからこそリコは、そこで遅れて避難してくる者がいないか、待ち続けていた。一緒にいる中核メンバーはリチャードだけだ。西側はボーイとワイズに任せ、ジン、アケミ、リトルジョンを始めとする他の面々には、メンタルケアに走ってもらっている。リコたちも単に待っているわけではなく、これからについて考えながら、策を練っている最中だった。
だからこそ、攻略隊の隊長が現れた時も、最初は気づかず、「あっ」と思ったほどだ。
同時に「あれ?」とも思った。
白髪痩身、黄金の双眸を宿すレイスという名のプレイヤーは、どういうわけか、T字路の中央に立ち、ジッとエレベータールームに通じる通路を見つめていたのだ。
彼だけではない。気が付けば手が空いたらしい、他の隊員たちも姿を現していた。
(――もしかして、全員?)
二十人以上いる。その全員が、ジッと、通路の向こう側を見据えていた。
異様な光景だ。
リコばかりでなく、近くにいる独立派の面々も、重い空気を察して口をつぐんでいた……
「……あっ」
誰かが声をあげた。
リコは通路の奥に視線を向けた。
人影があった。
数は二つ。並んで歩く人影は、ゆっくりとこちらに近づきつつあった。
(あれが……)
リコは改めて目を見張った。
小柄な少年と、小柄な少女だ。年の頃は十四、五歳。背丈は少しだけ、少年のほうが高いようだ。ただ、まったく同じ装備を身につけているため、どことなく兄弟姉妹のような印象を感じた。
膝当てと一体化した黒いロングブーツ。
ゆったりとした黒いズボン。
艶消しされた黒いバックルに鷹の意匠を施した革ベルト。
躰にフィットする袖無しのハイネックシャツ。
少年のほうは左腕から肩を経て、頬にいたるところまで炎の刺青を施していた。
少女のほうは丈の短い、黒いレザージャケットを羽織っている。
少年の左腰にはカタナが差してあった。
少女は右手に薙刀を持っていた。
二人とも表情は真剣そのものだ。いずれの瞳にも、強い決意の輝きが宿っていた。
そして――攻略隊の面々は、黙り込んだまま二人がやってくるのを待ち続けていた。それもまたリコからすると「あれ?」と思わずにいられない光景だった。少なくとも、少年のほうは、十日間ほど失踪していた仲間のはずなのだ。それに少女のほうは、自治会につかまり、監禁されていた仲間のはずである。もっと喜んでもおかしくない瞬間のはずなのだが……
いや、最初の一瞬だけ、彼らの顔には喜びの表情が浮かんだ。
だがそれも、次の瞬間には険しさに代わり、苦渋へと変わった。
(……犠牲者でも出たの……かな?)
よく見ると、少しだけ皆から離れたところに聖職者っぽい女性プレイヤーが立っていた。美形とはいえないが、傍目には可愛らしくも見えるポッチャリ系の女性だ。彼女だけは、単なる苦渋を通り越えて、グッと歯をくいしばりながら顔を背けているようだ。少年と少女を見つめていない攻略隊メンバーは彼女ただ一人であるらしい。
(……そうか)
そういえば例の少女がつかまった時、メンバーの一人がロスト、もう一人が自治会に寝返り、あまつさえたった数日でナンバースリーの座にまで上り詰めたとか――そんな話を耳にした記憶がある。おそらくは、そのあたりに関係があるのだろう。
(素直に喜べないっていうのも、辛いよね……)
リコは複雑な思いを抱きながら、改めて少年と少女のほうに視線を向けてみた。
近づいた二人が立ち止まったのは、それから間もなくのことだった。
張りつめた空気が漂った。
沈黙を破ったのは、少年のぶっきらぼうな物言いだった。
「――道連れが欲しい」
間髪入れず、レイスの手が動いた。
――パーン!
見事な平手打ちだ。だが、コロシアムでの常軌逸した戦いを見ていたリコにしてみれば、どうして少年が避けなかったのかと思わずにいられなかった。
「最初に言うべきことがあるだろう!」
レイスが怒鳴った。
頬を叩かれた少年は、顔を少しだけ背けたまま、グッと口元を引き締めていた。
隣りに立つ少女は、そんな少年の横顔を見つめている。
少年は目元に力を入れ、それから深々と頭を下げた。
「……ごめん」
「それで済むと思ってるのか!」
「………………」
「どれだけ迷惑をかけたか、わかってるのか!?」
「……ごめん」
「この大馬鹿者!」
レイスは少年の髪を乱暴に掴みあげた。
「悩むぐらいなら誰かに相談しろ! ひとりで抱え込むな! そんなに私たちが信用できないのか、おまえは!」
「………………」
「この……大馬鹿が!」
レイスは――少年を抱きしめた。
「この……この…………」
「……ごめん」
他の面々が動いた。無言のまま歩み寄り、少女と抱き合ったり、少年の背中を叩いたり、何も言わず涙ぐんだり――それは、あまりにも静かすぎる再会劇だった。だが、そこに宿る思いの強さは、第三者であるリコでさえも、痛いぐらい感じ取れるのだった。
◆
「身内だけで話したい。こちらから外に出るまで、誰もドアに近づかないでくれ」
レイスはそう告げ、独立派を泉部屋から遠ざけた。こうして泉部屋の噴水と寝床の間に、二十六名になった攻略隊のメンバー全員が再集結することになった。
「最初に断っておく」
噴水に腰掛けたレイスは目を閉ざしながら訥々と語った。
「慣れのせいで忘れかけているが、我々は仮想現実世界に閉じこめられるという異常な環境に放り込まれている。たとえ意識していなくとも、それによるストレスで、我々は毎日少しずつ疲弊している。仮に誰かが常軌を逸した行動に出たとしても、それはストレスが原因である可能性が高い。我々は危ない橋を渡り続けているんだ。だから……誰のせいだとか、誰が悪いとか、そういうことは考えないで欲しい。気持ち的に納得がいかなくとも、全員で行動している時は、無理矢理にでもそう納得してくれ。愚痴なら、私が聞く。だから頼む。そういうことにしてくれ」
反論は無かった。
ただ、様々な姿勢で座る隊員たちは、自らの意志でレイスの真正面に座ったマサミの背中を一瞥せずにいられなかった。ある意味において、彼女の行動こそが、様々な出来事の直接的な引き金だったのだ。彼女がクロウを躰で誘惑しなければ、追いつめられたクロウが逃げ出すことも無かった。バッシュが死ぬことも、マコが洗脳されることも、リーナが囚われることも……
「隊長」
そのマサミが、口を開いた。レイスは目を開け、真正面に座る彼女にうなずき返した。
彼女は立ち上がった。
「私、隊を抜けます」
「……ダメだ」
「独立派に入ります。今日まで本当にお世話になりました」
「……許さないと言ったら?」
「死にます」
それは、とても自然に出た言葉に聞こえた。
「ここで死んでも本当に死なない可能性、あるんですよね。隊を抜けられないなら、その道を選びます。後ろ向きかもしれないけど、私、これ以上、一緒に戦えません。きっとみんなの足を引っ張るから……」
「残されたほうはどうなる。どっちにしろ、イヤな思いが残るだけだぞ」
「でも、私がいなければ、私のこと、気兼ねなく憎めますよね?」
レイスは黙り込んだ。
誰もが顔をしかめ、口を閉ざし続けた。
だが、マサミだけは――自ら嘲笑うかのように――口元に笑みを浮かべていた。
「心配しないでください。私、みんなのこと、信じてます。自殺したりしません。本当にお世話になりました」
マサミはウィンドウを開き、レイスの前にボールオブジェを次々と置いていった。
誰もが何も言えず、その作業が終わるのを待った。
しばらくすると、マサミは基本装備のTシャツにベスト、ロングスカートにサンダルという恰好になった。武器も防具も、すべて差し出したのだ。そして彼女は、今日までありがとうございました、とレイスに頭を下げて、泉部屋の外に出て行った。
静寂が残された。
寝床際の定位置に座るクロウと、その隣りに座るリーナだけは、隔壁が閉まるまで、ジッとマサミの背中を見送り続けた。マサミが陵辱されたことを知るのは、それを目撃したクロウと、第一階層のダークゾーンで、彼からその話を聞いたリーナだけだった。
(……恨めないよ、これじゃ)
リーナは心の中で、ここにいないマコに向かって語りかけていた。
◆
もうひとり、離脱者が現れた。
「これからやること、想像がつくんでね。悪いけど、遠慮させてもらうわ」
立ち上がったのは――キリーだった。
これには誰もが驚愕した。
「……おまえもか」
レイスは苦しげにつぶやいた。
「えぇ、俺もですよ」
外見こそは普段通りの妖艶な美女だが、今のキリーは霧島豊に戻っていた。
「……キリー、念のために尋ねておく。想像がつくといっていたが、おまえが予想した『これから』とは、なんのことだ?」
「クロウ。十階に直行するんだろ?」
キリーはレイスにではなく、振り返りながら、背後のクロウに尋ねた。クロウはジッとキリーを見返したが、小さく一度だけうなずき返した。
「九階まで降りるエレベーター、みつけたんだな?」
「……それらしいものと、コントロールセンターらしきもの」
クロウはボソボソと答えた。
リーナが口添えする。
「あたしも見た。多分、間違いないと思う」
独立派の避難誘導を続けている間、クロウとリーナは第一階層のエレベータールームに向かい、直接、第四階層を確かめに戻っていた。エレベーターの利用にはレベル制限がついているものの、パーティメンバーが一人でもクリアしていれば使用可能になるという緩い制限だったおかげだ。独立派の避難も、これを利用し、レベル三十を越えている攻略隊の面々が第三階層まで連れて行ってはパーティ解除、戻り、パーティを組み、連れて行ってはパーティ解除――という作業を続けることで短時間に終えられたのだった。
「なんだ? まだ“ブルーリボン”、手に入れてないのか?」
キリーの言葉に、クロウは苦しげに首肯した。
「敵の数が……俺一人じゃ、無理だと思う。だから――」
「『道連れが欲しい』、か」
キリーは帰還直後のクロウが口にした台詞を繰り返した。
「……まっ、おまえにしちゃ、上出来だな。限度ってもんを見極めたわけだし」
「まったくだ」
口を挟んだのはレイスだ。どことなくホッと安堵しているようにも見える。
だがクロウは、
「……リィに止められた」
と不満げにつぶやいた。
これには皆が、小さくだったが笑った。
「おいおい、しっかりしろよ」キリーも苦笑をもらしている。「だいたい、俺にしても見限るつもりじゃないだからな?」
「……だったらどういうつもりだ?」
レイスは責めるわけでもなく、素朴な疑問を投げかけるように尋ねてみた。
「ガラじゃないけど……バッシュの遺言、試してみようかなぁって」
「……ルーマーシステムか」
レイスの顔に、ようやく普段通りの冷笑が浮かんだ。
「それそれ」
キリーは歩き出しながら、言葉を続けた。
「噂を流すんなら、関係者の一人や二人、残るべきってもんだし。まぁ、どこぞの誰かさんがコロシアムでかなり派手に暴れてくれたんで、尾ひれを付けてやるだけで大丈夫かもしれないけど。あぁ、行く前に犯りたいヤツ、ハッテン場にいるから来たい時に来ていいぜ。サービスしてやっから」
キリーはそのまま泉部屋を出て行った。
呆気ない最後だった。
「まったく……」
レイスは冷笑に見える苦笑いを浮かべながら、ワシャワシャと白い髪を軽くかいた。
「他にいるなら、今のうちだぞ」
離脱者は現れなかった。
To Be Contined
Copyright © 2003-2004 Bookshelf All Right Reserved.