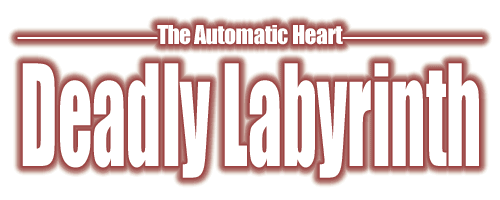
[18]
それは殺戮だった。
「くるぞ! 重戦士、構え!」
男性外装の魔術師が叫ぶと同時に、前列に出ていた重戦士たちが盾を構えた。
獲物が爆煙から飛びだしてきたのは、その直後のことだ。
黒い疾風だった。
盾のひとつを踏み台にしたそれは、軽々と重戦士の壁を乗り越え、三メートル四方の一ブロック部屋のただ中、二十四名の魔術師が六名ずつ四列に並ぶ中へと飛び込んできた。
最初に、しゃがんでいた二列目中程の魔術師の頭が踏まれた。
そのまま彼は悲鳴をあげて倒れた。
黒い疾風は白刃を振った。
左右ひとりずつ、三列目のふたり、計四人の首が胴から切り離された。
悲鳴があがった。
だが、誰もが何が起きたか理解していない。指示も飛ばない。当然だ。最初の犠牲者の中に檄(げき)を飛ばしていたリーダーがいたのだから。
疾風のさらなる白刃。
宙を飛ぶ頭。
逃げ出す魔術師たち。
前方の重戦士六名が対処しようとする。だが、逃げまどう魔術師たちが邪魔になった。それでも魔術師たちを押しやり、疾風に迫ろうとする。その押し合いが混乱を広げた。
後方も同様だ。重武装の聖職者たち十二名は、回復魔法を放つべきか手にした武器で殴りかかるべきかで戸惑ったのだ。そこに、最後列の魔術師が逃げ出してきた。パニック状態の彼らが邪魔で、黒い疾風――人型クリーチャーの動きすらよく見えなかった。
その間も疾風は白刃を振るった。
逃げ惑う魔術師が次々と一撃で葬り去られていく。
放つ攻撃、全てがクリティカル。
黒いズボン、黒い袖無しシャツ、濃褐色の肌、ボサついた黒い髪、両腕には炎の刺青、頬にも炎の刺青。黒い瞳は見開かれている。食いしばった歯をむき出しにしながら刃を振るい続けている。
ニンジャだ。『WIZARD LABYRINTH』の様々なギミックが、史上初のコンピュータRPG『Wizardly』のオマージュであるのは有名な話だ。その話題は、何度となく彼らの間でも出ている。
ニンジャは『Wizardly』でも最悪のモンスター。
強さだけなら他にもっと強いモンスターがいる。だが、ニンジャにはクリティカルヒットがある。
首刈り。
レベル九十九の最強キャラクターであっても、一撃で殺してしまう最強無比の攻撃手段。
それだ。
誰もがそう思った。
こんなことなら志願するんじゃなかった。エレベーターとブルーリボン。『Wizardly』にある、より簡単に地下に向かう手段。効率の良い狩場への移動手段を探す集団に加わるんじゃなかった。いくら報酬が良かったからといって。
「に、逃げろ!」
誰かが叫んだ。
聖職者たちが逃げ出した。生きていた魔術師たちも逃げ出す。
一列目の魔術師は逃げられない。そもそも彼らはすでに死んでいる。
重戦士たちも逃げ出せない。すでに三人が鎧の隙間から四肢を切られ、さらには首も刈られている。残る三人は奇声をあげながら黒い疾風に襲いかかった。
だが、武器が攻撃阻止限界点に達する寸前に疾風の躰は別の場所に移動する。
かと思うと手首が消えている。
切られた。
刈られた。
疾風が吹き抜ける。
死が量産される。
黒い疾風が吹き荒れる――
◆
「――ハァ、ハァ、ハァ、ハァ、ハァ」
全てが終わると、そこにはカタナを手にするクロウの姿しか無かった。
犠牲者たちはすでに消滅済み。彼らの名残は、ひとり一個ずつ残していったボールオブジェ――装備とアイテムが詰まったもの――だけになっていた。具現化させることはできないが、十分以内にウィンドウに収納すると倒したプレイヤーの全装備、全アイテムが自分のものになる。それが『WIZARD LABYRINTH』のPvP(プレイヤー対戦)のルールなのだ。
だが、クロウはボールオブジェを拾おうともせず、のろのろと四×四ブロック部屋の中へと踏み出していった。
彼が通り抜けると、今更のようにドアが音をたてて締まり出す。
爆煙は張れていた。
リーナは部屋の一角で、胎児のように丸くなって倒れていた。その上に浮かぶオーバーヘッド・ステータスによると、負傷こそしているが、HPバーの色はまだ黄色に突入したばかりらしい。
クロウはカタナを手にしたまま彼女のもとに向かった。
近づいていると、リーナは両足首を掴んだ姿勢で、ジッとどこかを見据えていた。
(良かった……)
クロウは崩れるように彼女の傍らで両膝をついた。
手からカタナが落ちる。
「はぁ…………」
そのまま彼はあぐらをかいた。
ガクリと項垂れ、後ろ頭をガリガリとかきはじめる。
「……プレイヤーだった?」
リーナがポツリと尋ねた。
「あぁ」
「……殺した?」
「殺した」
「……いっぱい?」
「いっぱい」
「……どんな気分?」
「実感無し。死体も残らないだろ。だから」
「……黒い」
「んっ?」
「名前。クゥの」
見上げると、頭上のキャラクターネームが黒くなっていた。おまけに名前の頭には髑髏(どくろ)のオブジェまで浮かんでいる。初めてみるものだが、何となく意味するところは理解できた。
「殺しまくったからなぁ……」
それでも実感が持てない。自分が人を殺したという実感が――
「ごめん」とリーナ。
「んっ?」
「また……」
「……また?」
「コロシアムでも……」
「……あぁ」
そういえばそんなこともあった。
「結果的にそうなっただけだろ。あの時も最後は俺が狙われたからやり返しただけだし。今回だって――あんだけやられたら、そりゃあ、やり返すだろ、普通」
リーナは黙り込んだ。丸まったまま、ピクリとも動こうとしない。
なんだか嫌な感じだ。
喘息持ちだと明かした時と似ている。あれほど明るく口の減らないリーナが、まるで……まるで…………
「あっ……」
クロウの小さなつぶやきだけで、リーナは全身をびくりと振るわせた。
「いや、あれだな」
クロウは再び後ろ頭をガリガリとかく。
「病院で……喘息の頃にさ、病院に通ってた時、すげー明るいヤツとかいるわけよ、どうみても長期入院してるヤツなんだけど。でも、たまにそいつが病室にひとりでいる時とか見ることがあって……」
クロウは深呼吸をした。
「おまえ、話したくないんだな?」
なにを――とは言わない。
尋ねてはいけない。
強いヤツほど脆い。クロウ――烏山浩太郎は、経験則としてそういう人間がいることを知っていた。なにしろ自分からしてそうなのだから。強がらなければ、悲しすぎたのだから。
「……ごめん」
数分後、ようやくリーナはポツリとつぶやいた。
(……足か)
リーナはしきりにふくらはぎをさすっている。失ったのか、動かないのか、何なのかサッパリわからないが、それでも足に絡む何かを抱えていることだけはわかった。
(足……?)
――ジークンドーと新体操。あたしがやってたスポーツ。アクションスター目指してたの。
リーナはそう告げていた。
過去形で。
「………………」
つまり、そういうことなのだろう。
「わかった」
クロウはウィンドウを展開させつつ、できるだけさりげない口調を心がけた。
「話したくなったら話せよ。俺がイヤなら、レイスにでも」
――ガガガガガガッ
ドアがせり上がる。
リーナは丸まったままハッと目を見開き、クロウは舌打ちをしながら転がしたカタナを拾った。
「リィ、そこ動くな。いいな、絶対だぞ」
「クゥ……」
彼女が躰を起こすと同時に、クロウはウィンドウから取り出したヒールクリスタルを自らの胸に叩きつけた。
「絶対だぞ」
カタナを鞘に収め、ドアに向かって走り出す。
(この部屋に一歩たりとも――!!)
と彼が意気込んだまさにその時。
「クロぉ―――――――――――――――――――――――――――――――――ウ!」
「リーナぁ――――――――――――――――――――――――――――――――ぁ!」
ドアの隙間から響いてきたのは聞き慣れた声だった。
「うへっ!?」
クロウの足から力が抜ける。途端、彼は無様にスッ転んだ。そのままゴロゴロとドアの前まで転がってしまう。
「あっ、いたいたいたぁ!」
「隊長ぉ! みんなぁ! こっちでーす!」
「クロウ! まさかリーナちゃんを襲ったんじゃないだろうな!?」
まだドアが開ききる前から次から次と攻略隊の面々が滑り込んできた。
転んだ拍子に大の字に寝そべる形になったクロウは、ヒョイッと顎をあげ、奥のリーナに視線を向けた。躰を起こしていたリーナは目を点にしていたが、そんなクロウと目をあわせた途端、急にプッと小さく噴き出している。
「笑うな」
「だって」
距離があるうえ、小声でつぶやきあったのだから声が届くわけがない。だが、その時のふたりは間違いなく、お互いの声を聞きあい、互いに頬を緩ませていた。
(目的追加……か)
クロウは心の中で小さくつぶやいた。
生きて帰る。
早く姉に会う。
そして――リーナを守る。何があっても。
To Be Contined
Copyright © 2003-2004 Bookshelf All Right Reserved.